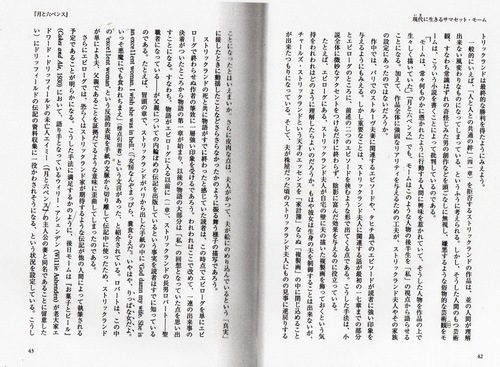- 06
- 22
『現代に生きる サマセット・モーム』
『現代に生きる サマセット・モーム』
モームの主人公に托した真意
結局、ストリックランドは、自分自身の作品を完成させることによって、ようやく己の魂を解放させたようだ。自分だけでなく、他人をも犠牲にすることで、さらには人間的なしがらみをすべて断ち切ることによって,ストリックンドは最終的な勝利を得たようにみえよう。
一般的にいえば、「人と人との共通の絆」を拒否するストリックランドの作品は、並の人間が理解できない風変りなものになってしまっている、という風に考えられる。しかし、そうした人間の持つ芸術観、すなわち常識はずれの奇怪じみた男の創作などを頭ごなしに無視し、嫌悪するような俗物的な芸術観をモームは、こういう小説を書くことによって批判しているのである。(清水)
(そうですね。生きていて人が認めなければ その時は理解できないとか 風変りとか言われたりするということですね。そして 死して 何年かして幸いなことに評価が高まり 評論家は騒ぎ出し その作品の一枚とも見落とすまいとする。ストリックランドの気難しいところもそれはかえって 人を惹き付ける風に評価は変っている。これはゴッホにしても そうだろうなと思ったりしますが。
そんな真の(どういうのが真の絵なんだろう) 絵を描きたい 残したい画家達が いっぱいいたのではないだろうか。そして現代も。(ヒエー!言っちまった。その前にそんな絵を描けっちゅうの)
モームは、常々何者かに憑かれたように行動する人間に興味を惹かれていて、そうした人物を作品の上で生々しく描いていた。『月と六ペンス』でも、モームはこのような人物の後半生を「私」の視点から語らせることになる。加えて、作品全体に強固なリアリティを与えるための工夫が、ストリックランド夫人やその家族の設定にあったのではないだろうか。
(なるほど。私はこの小説で興味深かったのは タヒチに行くまでのストリックランドがどういう風だったのかを知ったことでした。その家族のこと夫人のこと友達のことなど。)
作中では、パリでのストルーヴ夫妻に関連するエピソードや、タヒチ島でのエピソードが読者に強い印象を与えるようにもみえる。しかし重要なことは、ストリックランド夫人に関連する話が最初の十七章までの部分とエピローグのところに、前述の二つのエピソードをはさむような形で出てくる点である。こうした手法は、小説全体に微妙なアクセントを付けるだけに終わらず、陰影に富んだ効果を与えるのに役立っている。
(清水)
(読者の自分は ストリックランドの家族が こうしたストリックッランドの死と そのご 有名になることに どういう反応を示すのか 著者はどう書くのだろうとこの最後の話を読んでいました。
しかし あくまでも このストリックランドの側にいるのだった というのが私の思いでした。)
たとえば、エピローグにある、ストリックランド夫人が自宅の壁に夫の描いた複製画を飾っておくという気持をわれわれはどのように理解したらよいのだろうか。(清水)
(これは 今の時代なら いかようにも 想像できると思いますね。夫人はもう夫とは ふっ切れているのかもしれないとか その絵の内容についてさわぎだす(以前のように)事はしないと決めていたのかもしれないし。
個々のシーンについて 女性がどう見るか 読んでみたいですね。夫が有名になったからって いろんな人に 聞かれても答えているのは 彼女の中には彼が亡くなるまでいろんなことを経験しただろうけれども
彼の家庭はここにあると思っていたんじゃないだろうかとか。一人の画家としての資料として 話したんじゃないだろうかとか。
子供らも 父親が出て行った後 つらい思いをしなかったということはないと思います。そのある意味悲惨な最期を複雑な受け止め方をしても不思議じゃないと思うんですけど。この小説の最後に入れたこの章については。)
もはや彼女は生身の夫を制御することは出来ないが、チャールズ・ストリックランドという天才のエッセンスを「家計簿」ならぬ「複製画」の中に閉じ込めることが出来たつもりになっている。そして、夫が株屋だった頃のストリックランド夫人にものの見事に逆戻りすることになったととはいえまいか。さらに皮肉な点は、夫人がかって、夫が絵にのめり込んでいると言う「真実」に接した時に動揺したことなどさらさらなかったように振る舞う様子の描写であろう。(清水)
(「そうか、これはモームさんの小説なんだ 彼の考え思いを書いているんだ」私は清水さんの話に 気がつくのです。この夫人がどう想うかは あまり考えちゃいけないんだと。そして 著者の考えは実生活から来ているのかもしれないし。それぞれの考があるのだ」)
我々は個々であらためて、一連の出来事の決着がついたところから物語の第一章が始まり、以後の物語の大部分は「私」の回想となっていた点を思い出すことになる。すなわち、物語がエピローグに入る以前に、ストリックランドの長男ロバートー聖職者になっているーが父親についての内輪簿目の伝記を出版しているという事実を読者は既に知っているのである。(清水)
(忘れてる!だいたい 長男ロバートは聖職者になっていたんですね、前に私は軍人になっていると書きました まちがいですね すみません。やー 清水さん ちゃんと読めていません自分は)
たとえば、冒頭の章で、ストリックランドがパリから出した手紙の中に「女房なんぞまっぴら、糞食らえだ。いやはや、立派な女だよ。いっそ悪魔にでも喰われちまえ」という文言があった、と紹介されている。ロバートは、このなかのexcelllent womanという反語的表現を手紙の文脈から切り離して伝記中に使ったため、ストリックランドが単によき夫、父親であることを証拠だてるような意味に歪曲してしまったのである。
(もう、忘れています。しっかり読め!ノリコ ここらあたりからもうこの小説について何か言うことができなくなっちまって)
さらにエピローグでは、恐らくはストリックランド家が期待するような伝記が他の人間によって執筆される予定であることがあきらかになる。こうした手法に満足するかのように、後日モームは『お菓子とビール』において、語り手となっているウイリー・アシェンデンが老大家エドワード・ドリッフィールドの未亡人エイミー(『月と六ペンス』の主人公の妻と同名であることに留意したい)にドリッフィールドの伝記の資料収集に一役かわされそうになる、という状況を設定している。(清水)
(伝記というものは死者をどう見ていたかが 人によって違うということなんですね。本人の日記でものこされていない限り。それでも「それぞれ」というのがあたっているのかも。)
*
ストリックランドの絵についても 著者のみかた ほかの人のみかた いろいろあるでしょうが これはその作品に出会った読者や絵を見る人たちは それを自分にひきつけて考えてみたりできるのですね
『月と六ペンス』は自分にとって たとえストリックランドが 今では歴史にのこる芸術家であっても
自分のこととともに考えさせてくれる貴重な小説でした。
《 2021.06.22 Tue _ 読書の時間 》