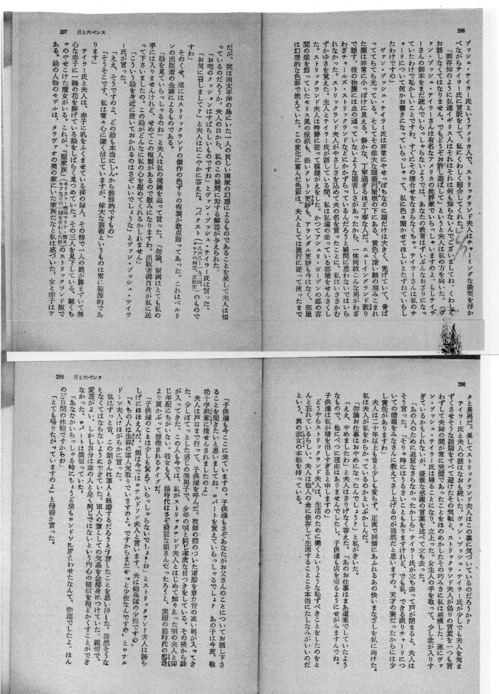- 06
- 08
モームさん
ヴァン・ブッシュ・テイラーというアメリカ人にストリックランド夫人のところ(ロンドン)で会う。批評家でストリックランドについて何か書いているらしい。
夫人の壁にはストリックランドの傑作の色ずりの複製が数点飾ってあった。部屋は幻想的な色彩で燃えていた。この変化に富んだ色彩は、夫人としては流行に従っって使ったまでだが、実は南太平洋の島ににいた独りの貧しい画架の幻想によるものであることを果して夫人は知っているのだろうか。
「お宅のクッションはすばらしいものですね」とヴァン・ブッシュ・テイラー氏は言った。
「お気に召しまして?」
と夫人はにこやかに答えた。「バクスト(1868−1924、ロシアの画家、意匠家)のものですわ)
夫人の壁にはストリックランドの傑作の色ずりの複製が数点飾ってあった。(再び)
「絵を見ていらっしゃるのね」と夫人は私の視線を追って言った。「勿論、原画はとても私の手には入りませんけれど、せめてこの複製があるので慰みになりますわ。出版者御自身が私に送って下さいましたの。この絵がどんなに私の心を慰めてくれるかしれません」
「こういう絵を身近に置いておかれるのはさぞいいでしょうな」ヴァン・ブッシュ・テイラー氏が言った。
「ええ、そうですのよ、どの絵も本当にしんから装飾的ですもの」
「そうそこです、私は常々心に深く信じていますが、偉大な芸術というものは常に装飾的であります」
テイラー氏と夫人は、赤子に乳をふくませている裸の夫人、その傍で一人の娘が膝まずいて無心な赤子に一輪の花を捧げている絵をしばらく見つめていた。その三人を見下している、皺くちゃのやせこけた魔女がいる。これが、『聖家族』(キリスト・聖母マリア・聖ヨセフなどの一団を表した絵)のストリックランド版である。絵の人物のモデルは、タラヴァオの奥の家にいた家族だなと私は感づいた。女と赤子はアタと長男だ。果してストリックランド夫人はこのことに気づいているのだろうか?
テイラー氏と夫人の話はなおも続いた。ヴァン・ブッシュ・テイラー氏が少しでも夫人を気まずくさせそうな話題をすべて避けたその気転と、ストリックランド夫人が偽りの言葉を一つも言わずして夫婦の間が常に完璧であったことをほのめかしたその巧みさに私は感嘆した。遂にヴァン・ブッシュ・テイラー氏は帰ることになり、立上がった。女主人の手を取って、少し念が入りすぎているかもしれないが、優雅な感謝の言葉を述べて立ち去った。
「あの人のために退屈なさらなかったかしら」テイラー氏が立ち去って戸が閉まると、夫人はそう言った。
「そりゃ時にはうるさいときもありますけれど、でも私、できる限りチャーリについての情報をみなさんに教えてさし上げるのが当然だと思いますの。天才の妻だったからには少し責任がありますわ」
夫人は二十年以上も昔と少しも変らず、正直で同情にあふれるあの快いまなざしを私に向けた。
私は夫人が私をからかっているのかといぶかしんだ。
「勿論仕事はおやめになったんでしょう?」と私がきいた。
「ええ、やめましたわ」と夫人はさりげなく答えた。「あのお仕事はまあ道楽でしていたようなもので、他にべつに理由はありませんでしたし、子供達も店を売るようにせがみますんでね。子供達は私が精を出しすぎると申しますの」
どうやらストリックランド夫人は、生活のために働くというような恥ずべきことをしたのをとんと忘れているらしい。夫人は他人の金に依存して生活することこそ本当にたしなみがいいのだという、真の淑女の本能を持っている。
「子供達も今ここに来ていますの。子供達もさぞあなたがお父さんのことについてお話下さることを聞きたいと思いましてね。ロバートを覚えていらっしゃるでしょ?あの子は今、戦功十字勲章に推せんされましたのよ」
夫人は戸口まで行って、子供達を呼んだ。牧師の襟のついた軍服を着た背の高い男が入ってきた。少しぼてっとした感じの美男子で、少年の頃と同じ素直な眼つきをしている。その後から妹が入って来た。この人も今では、私がストリックランド夫人と始めて知りあった頃の夫人と同じ年配にちがいない。彼女も又、娘時代にはさぞ奇麗な娘さんだったろうと、実際の娘時代の器量より買かぶって想像されるタイプだ。
「子供達のことは少しも覚えていらっしゃらないでしょうね」とストリックランド夫人は誇らしげにほほえんだ。「娘は今ではロナルドソン夫人と言います。夫は砲兵隊の少佐ですの」
「うちの人は生粋の軍人気取りでいますのよ。ですからまだやっと少佐なんですの」とロナルドソン夫人はほがらかに言った。
私はずっと昔、この娘さんは軍人と結婚するだろうと予想したことを思い出した。当然そうならなくてはならないようにできていた。軍人の妻としての気品を全部身につけていた。親切で、愛想がよい、しかし自分は並の人と全く同じではないという内心の確信を殆どかくすことができなかった。
ロバートは張切っていた。
「あなたがいらっしゃる時にちょうど僕もロンドンに居合わせたなんて、幸運でしたよ。ほんの三日間の休暇ですからね」
「とても帰りたがっていますのよ」と母親が言った。
*
「わたし」がタヒチでのストリックランドの話を現地で聞いたこと これを読んでから こうしてロンドンのストリックランド夫人息子や娘の話はいっそうストリックランドが 出て行ったことがわかるような気がします、いや この関係でなくても彼はきっと とりつかれたように出て行ったのだと。タヒチでもアタが彼に何も求めなかったから 描きつづけたんですよね 求めていたものがわかるまで。
いったいそれはなにだったのか。ふたたび後戻りしなければなりません。お客さん、言えますか?
いきつもどりつ そのくせ ストリックランドは絵で表した人なのだから。 クトラ医師の感想などから想像する他ないのですから。彼はなににやっとたどりついて 死んで行ったのか。
さて あと一ページで終ります。
《 2021.06.08 Tue _ 読書の時間 》