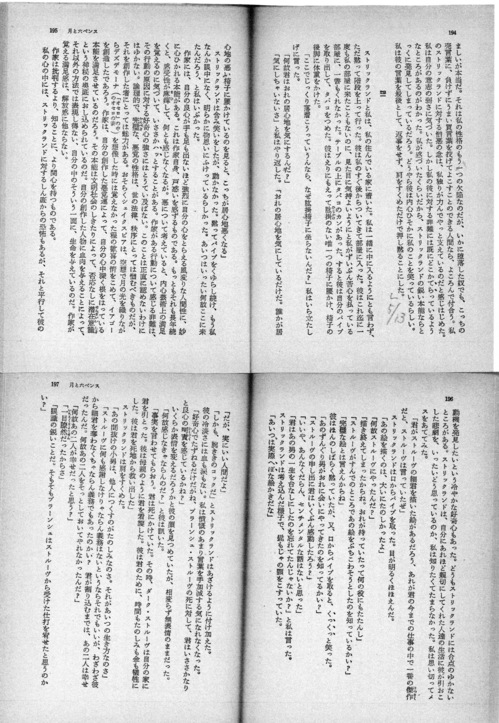- 05
- 14
モームさん
あさひがだいだい色の強い光を放っていました。あさひにあたるといいんだよとは聞いていますが
このあさひの濃さは どうしてなのとききたくなります。あさひにスタートはあるのかな?
作家には、自分の良心が手も足もでないほど強烈に自分の心をとらえる風変わりな人間性に、妙に心魅かれる本能がある。
悪について考えていると、内心芸術j上の満足を覚えるのに気づいて、いささかはットすることがある。
作家がある行動について感じる非難は、その行動の原因に対する好奇心の強さにはとうてい及ばない。
論理的で、完璧な、悪党の性格は、世の法律、秩序にとっては憎むべきものだが、それを創作した者にとっては魅力がある。
作家は自分の創作した悪党連によって、自分の心中深く根をはっている本能を満足させているのだろう。その本能は文明社会のしきたりによって、否応なしに潜在意識という神秘の奥底におし込められているのだ。自分の創作した人物に血肉を与える事によって、それ以外の方法では表現し得ない、自分の中のそういう一面に、生命を与えているのだ。作家が覚える満足感は、開放感に他ならない。
(そうなんだ」
作家は批判するより、知ることに、より感心を持つものである。
(作家じゃないけど自分も 人や自分のどういうところの興味を持っているのか知りたくなった)(ひはんするより知る事に興味を持てば 面白いのかも)
「いったい何故ブラーンシュ。ストルーヴなんかにかかわり合ったんだ、聞かせてくれないか?」
「そんなことわかるもんか」「あの女はおれなんかみるのもいやだった。それが面白かったのさ」
「ええい、沢山だ、おれはあの女が欲しかったんだ」「はじめはおれをこわがっていた」「田が遂におれは手に入れた」
まるで彼の肉体が精神に時々おそろしい復讐を加えているかのようだ。彼の中にひそむサター的な面がいきなり彼を占有する。すると彼は原始的な自然の力と同じ激しさを持つ本能のとりことなって、手も足もでなくなってしまう。これほど彼をとらえてしまう執念はない。だから彼の心の中には、思慮とか感謝など入り込む余地はなくなってしまうのだ。
(なるほどと言いたいけれども よくわからない)
「あの女はすばらしい体を持っていた。おれはヌードを描きたかった。絵を描き終えると、もうあの女には興味がなくなった」
「それなのにブラーンシュは心から君を愛していた」
「おれは愛なんか要らない。そんな暇はないんだ。愛は弱さだ。おれは男だから、時には女が欲しい。情欲を満足させてしまえば、もう他のことしか考えない。おれは欲望に勝てん。だが憎んでいる。おれの精神を束縛するからな。おれはすべての欲望から解放されて、仕事一本に打ち込めるようになる火が待遠しい。何故って、女は愛する意外に能がない。愛というものを馬鹿々々ほど重要だと考えている。それが人生のすべてだなどと男に思いこませようとする。愛なんてくだらん者さ。肉欲ならおれにもわかる。それは正常な健康なものさ。田が愛なんて病気だ。女はおれの快楽の道具だ。女共が内助者だの、協力者だの、伴侶だのになりたがるのには、我慢がならんのだ」
(こんな風に考えているのだな。ゆっくり考えてみよう)(本音というものがあるとしたら)
(愛と言う言葉、男と女 これはいろんな側面を持っている事がわかる)(上から目線やわ ストリックランド)
「何故あの二人が仕合せだったと思う?」
「一目瞭然だったからさ」
「眼識の鋭いことだ。そもそもブラーンシュはストルーヴから受けた仕打ちを許せたと思うのかね」
「それはいったい何の事だ?」
「何故ストルーヴがブラーンシュと結婚したか知らないのか?」
「ブラーンシュはあるローマ貴族の館に家庭教師をしていたんだ。ところがその家の息子に誘惑された。彼女はその息子が結婚してくれるものと思っていたんだ。ところが、その家から否応無しに身ぐるみおっ放り出された。彼女は妊娠していたので自殺しようとした。そこをストルーヴが見つけ出して結婚したんだ」
(ここのところぬけてた?)で(ブラーンシュはそれをゆるさないわけ?わからんわー、複雑やな)
《 2021.05.14 Fri _ 読書の時間 》